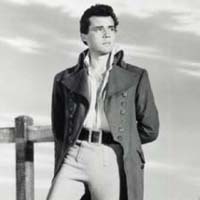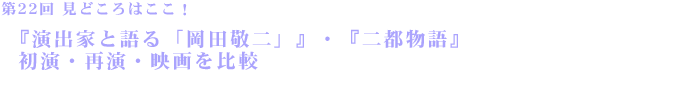 �@�����~�ł��ˁB���v���Ԃ�ł����A�݂Ȃ��܂����C�ł����H����̔ԑg�`�F�b�N�A�x���Ȃ��Ă��܂����̂ł����A11������������V���[�Y2��ڂ́w���o�Ƃƌ��u���c�h��v�x�ƁA�����Ɖf�悪���f���ꂽ�w��s����x����肠���Ă݂܂��傤�B�w��s����x�͍ŋ߉ԑg�ŏ㉉���ꂽ����B3����r���Ă݂����Ǝv���܂��B �@���c�h��Ƃ������}���`�b�N�E���r���[�V���[�Y�B���A���A�[�g�ȂǓƓ��̐F�ʁi�C�G���[��O���[���Ȃǂ̃N���A�ȐF�Â��������ꂢ�j�ƁA���蕶���̃^�C�g���A�����ėd�����Ɛ��X�����̗��ʂ�����������ʂ̐��X���v�������т܂��B�ǂ̍�i�ɂ���ڌ��������ł킩����Ɖ��₩����������Ă���̂ł����A�l�I�ɂ͂Ƃ��Ƀ^�J���d�J���S�҂̂Ƃ��ɖ����ɂȂ��Č����w���E�|�@�]���@���̛Z��x�i�����r������Č��K���o�ꂵ���I�f90�N���g�j�A�w���E�J���^�[�^�I�x�i�w�e���v�e�[�V�����I�x�̃^�C�g�����̗R���ƂȂ�����ʂł́A�����䂤�A���邠�₩�̐F�C�Ƀh�L�b�B�V�{�l�[������B�f94�N���g�j�����肪�Y����܂���B�l�I�W���p�l�X�N���́w���E�t���O�����X�x�i�f92�N���g�B�O�x�}�Œj�����x���Ă����I�j��n�[�h�{�C���h�^�b�`�́w�_���f�B�Y���I�x�i�f95�N�ԑg�B�����X�g���C�v�̃X�[�c�I�j�m�̃^���S�I�j�����I�ł����ˁB
�@���̃��}���`�b�N�E���r���[�V���[�Y�����N�̒��g�����w�e���v�e�[�V�����I�x�|�U�f�|��15�{�ڂƂ��B������L�O���āA�X�J�C�E�X�e�[�W�ł͉��c��i����W�B���}���`�b�N�E���r���[�V���[�Y����́w���E�p�b�V�����I�x�i�f89�N��g�j�A�w���E�t���O�����X�x�A�w���E�J���^�[�^�I�x�A�w�_���f�B�Y���I�x�A�w�V�g���X�̕��x�i�f98�N���g�j���o�ꂵ�܂�������A�݂Ȃ��\����܂�����ˁB �@�����Ă���Ɂw���o�Ƃƌ��u���c�h��v�x����������A���c�ƁA�w�e���v�e�[�V�����I�x�ɏo���������g�̎������Ɛ��ĊA���}���`�b�N�E���r���[�V���[�Y�ɂ��āA���c��i�ɂ��đ����ɒk�_�A�M��������ׂ��W�J���܂����B �u���c�搶�̃t�@���v�i���j�A�u���}���`�b�N�E���r���[�̃t�@���v�i���j�Ƃ���2�l��O�ɁA���c����1��w�W���e�[���x�i�f84�N�ԑg�j����15��ڂ́w�e���v�e�[�V�����I�x�܂ł̃��}���`�b�N�E���r���[�V���[�Y�̗��j��U��Ԃ�Ƃ����\���ŁA���ꂼ��ɂ��Ẳ��c�̑z���A���b�������[�������ł��ˁB3��ڂ́w���E�m�X�^���W�[�x�i�f86�N���g�j�́u�O�b�o�C�E�W�F�[���X�E�f�B�[���v�̏�ʂŁA�W�F�[���X�E�f�B�[���ɕ����������^�����Z���オ�����̂����āA���o���肾�����Ⴋ���̏��r�C��Y���܂����Ƃ����b�ȂǁA���̌�̏��r�̊����m�邾���ɁA������Ƃт�����̃G�s�\�[�h�ł��B�w�V�g���X�̕��x�́u�m�X�^���W�A�v�A�p�������ƂƘa���悤�������`�܂����荇����ʂ̃C���[�W���A���B�X�R���e�B�̉f��w�R�L�x�A�w�Ă̗��x���Ƃ����b�ɂ́A�����������̂��ƁA�v�킸���ł��܂����B�܂��w���E�t���O�����X�x�̐H���Ԃ̏�ʂ̃C���[�W���A���R�[�����b�g���痈�Ă���Ƃ͎v������炸�A�����������Ȃ�قǂƔ[���B�ŋ߃A�W�A�ւ̌X�|���ڗ����c�ł����A���̖G��͂��̕ӂ��炩�Ǝv������܂����B�A�W�A�Ƃ����f00�N�ԑg�́wAsian Sunrise�x������܂����A���c�ɂ̓��[���b�p�ł��Ȃ��A�����J�ł��Ȃ��A�A�W�A���̃^�J���d�J�Ǝ��̃��r���[��n��グ�����Ƃ����O�肪���邻���ŁA�wAsian Sunrise�x�p�[�g�U�����Ў������������Ƃ��B
�@���Ɛ��͂������Ƀt�@���Ƃ������������Ĕ������I�m�ŁA���Ȃǁu1��ڂ́w�W���e�[���x�ł���ˁv�Ɣ����Ԃ���I�B���c�����Ă̂���r�f�I�ł��낢�댩���炵���̂ł����A�u�w���E�|�@�]���x�ȂǑS���̂����Ⴄ���炢�v�����ɂȂ��������ł��B�܂����y�w�Z�̂���M�����u���T�y�j���A���Ƃ��I���ƌ���ɑ����Ă����Č��Ă����v�Ƃ������B�w���E�p�b�V�����I�x��w���E�|�@�]���x�Ȃǁu10�炢�͌��Ă��܂��ˁv�B �@�V���[�Y�ւ̏o���́A���̏ꍇ�A��g����́f96�N�wLa Jeunesse!!�x���ŏ��ŁA���͍���́w�e���v�e�[�V�����I�x���͂��߂Ăł����A��l�Ƃ����c���S�������x�����������o���҂ł�����A�܂����͏����䂪���c�S���́wBROADWAY BOYS�x�i�f93�N�B�g�~�[�E�`���[����E���o�j�ŁA��l�Ƃ����c��i�ɂ͐[����������܂��B �@��l�������ɂȂ����w���E�p�b�V�����I�x�A�w���E�|�@�]���x�B���}���`�b�N�E���r���[�̃Z�b�g�A�ߑ��A���y�Ȃǂ̃X�^�C�����m�����ꂽ�̂����̂�����ŁA�ŏ��ƍŌ�Ƀ^�C�g���̃Z�b�g���K���o�Ă���i�u�Ō�̕��͂��̂��뉺�낳�Ȃ���B�����ĉ��낵���Ⴄ�ƌ�1��2�̎q�̊炪�����Ȃ�����Ȃ��H�@���̂���͖l���N�Ƃ�������A���z�����牺�낳�Ȃ��v�j�̂��A���̂�����Ƀ��[�X�̃q���q�������Ă���Ɠ��̕ό`�������A���̂���m�����ꂽ�Ƃ��B �@����ȓ�l�ɂ��ẮA���c�̌��t���I�m�ł��B�{���ɐ��k�Ɉ������A�悭���Ă���l���Ȃ��Ǝv���܂����B �@���̃t�@�[�X�g�C���v���b�V�����́u�_���X���D���œ����Ă����l�v�B�u�O���̃��b�X���ɂ���݁A�n���ȓw�͂��d�ˁv�A����u���g�̃_���X�L���v�e���v�A�u���g���܂Ƃ܂��Ă���̂́A�j���͎�����A�����͋M���i�݂ǂ�j�����߂Ă��邩��v�B�u�F�̔Z�����̂��A�P�������A�ǂ�Ȃ��Ƃ��ė����Ă����v�ƃG�[���𑗂�܂��B�u�O���̌����������ς����Ă邶��Ȃ��H�v�Ƃ́A�������ɂ悭�m���Ă��܂��B���ꂩ��́u���������オ��悤�ȃ\�E���t���ȃS�X�y������肽���v�ƌ������B���c�ɂ��Ɓu�����ł��Ȃ��قǁA�⋩����悤�ɂ���Ă����B���������Ƃ��낪�������[�i���j�̂����Ƃ���v�B �@���Ɋւ��Ắu�ŏ����炱�̐l�͏�����w�����Ă����l���Ǝv���Ă��̂ŁA����ƂĂ��y���݂ł��v�ƍő�̎^���B�w�W���e�[���x�ő�Y�݂������x�����u�����v�̏��N������点�����Ƃ�����Ɍ����܂��B�܂��A�q�Q������������w�L�X�E�~�[�E�P�C�g�x�������A���b�N�~���[�W�J���������ƁA���҂��ӂ���ނ悤�ł��B�����g�̓^���S��x���Ă݂����Ƃ��B���܂ŗx�������Ƃ��Ȃ��Ƃ����̂ɂ́A���c���A�����Ď����т�����B�܂��w�����̌x�Ƃ��w�J�[�}���x�Ƃ��iAMP�ł��ˁj�̂悤�ȃX�g�[���[���_���X�œW�J���Ă����A�����������̂�����Ă݂��������ł��B �@�Ō�̉��c�́u�Ђ���V���[�Y�݂����ɂÂ������A���{�l�̍���h���Ԃ�悤�ȍ�i����肽���v�Ƃ������t����ۓI�ł����B
���āw��s����x�B����̉ԑg�������L���ɐV�����̂ł����A�����́f85�N���g�匀������B����̓C�M���X�̕����`���[���Y�E�f�B�P���Y�̓��������ŁA�f57�N�ɂ̓C�M���X�ʼnf�扻����Ă��܂��B�����ŃX�J�C�E�X�e�[�W�ŕ������ꂽ�����Ɖf��A����ɉԑg�����A�����Č�����r���Ă݂悤�Ǝv���܂��B�������������疟�Ȍ���i�ߑ㏬���m���ȑO�̍�i�ł�����A����̊�Ō���Ƃ��낢��^��_�������Ԃ̂ł��j�����ꂼ��ǂ������������A�����[�����̂�����܂��B
�@�܂������́A���g�匀������f���B�㉉����1���Ԕ��A�o���Ґ��������Ƃ��������̒��ŁA������V���[�A�b�v���ĕ��䉻���A�V�h�j�[�E�J�[�g����n�^���A���[�V�[�E�}�l�b�g���ؓ��A�`���[���Y�E�_�[�l�C���K�Ƃ����₩�ȃL���X�g�̖��͂��ő���ɐ�����������ł��B�����ł́A�㔼�̍ٔ��ɏœ_�����킹�A�J�[�g���̎��ȋ]���̔������ɏœ_�����Ă��Ă��܂��B���J���̓����h���ł̖��𒆐S�̃s�N�j�b�N�V�[���B�����Ɏ�v�L���X�g3�l���o�ꂵ�A����͈�C�Ɋj�S�ɔ���܂��B�����h���X�p�̍��̔������A�ԑ���������J����̑�n�A�w����������ƐL�����^�ʖڂ����Ȍ��A���ꂼ��̖��̃L�����N�^�[����ڂł킩�铱���ł��B����ɂ��Ă��A�b�v���ꂽ��n�̕\����͓I�Ȃ��ƁI�ݒc����m��Ȃ��̂ł����A���̌���I�Ȕ������͔��Q�B���͓��c2�N�ڂŎ���ɔ��F����A���̂Ƃ�5�N�ڂ̂͂��B����I�Ńi�`�������Ȕ��������ۗ����܂��B��n�ƍ��͂��̌����őޒc���A���̎剉�j���͌��ł����B���̌��͐h��������ʂ���̉��Z�Ō��点�A���͂ɓ]���āA���������Z�h�B3�l�Ƃ����͏��D�ł��ˁB���̑��A�}�l�b�g���m�ɓ��A��s�ƃ����[�ɖ����f���A�~�X�E�v���X�ɋ��O�сA�X�g���C�o�[�ɋ˂��Ǝ��A�h�t�@�[�W���ɐ����������A�e���[�Y�ɗL���~�ȂǁA��������������A�x�e�����ł�����Ă���l�̖��O�����т܂��B�����̃z�[�v�t���ЂƂ݁A�����܈��͌���ɂ͂Ȃ����Ō��ǂ��������Ă�����Ă܂��B�W�F���͋��^�R���ŁA���̖��͌���ł͉����̏����}�̂�������ł����A�������҂ɂ��Ď��j���ɓ��Ă�Ƃ����̂́A���o�Ƃ̑��c�N���̍H�v�ł��B�ԑg�����ł͉،`�Ђ��邪�����Ă��܂����ˁB�X�g���C�o�[�����Č���ł̓J�[�g���𗘗p���邾���̌��݂ȑ����ł����A�悫���_�ƃL�����N�^�[�����ρB�˂��y���ɉ����Ă��܂��B�������납�����̂́A����̉ԑg�����Ń}�l�b�g�������������̂��邪�A�����ł͈��}�o�[�T�b�g�������Ă��邱�ƂŁA�����炵�����S�҂Ԃ肪�A���܂��I�@���c�����i�悭�o�Ă���̂ł��j�u�T���L���[�E�x���[�}�b�`�v�ƁuI Can See It�v�i�w�t�@���^�X�`�b�N�X�x���j�́A����Q�O��ʂƃJ�[�g�����p�������܂悤�V�[���œo�ꂵ�Ă��܂��B����͉ԑg�����ł��Č�����Ă��܂����ˁB
�@�ԑg�����̓o�E�z�[�������Ƃ����ď㉉���Ԃ��啝�ɑ����A�o���҂���Ԃ��Ă���̂ŁA��{��V���ɏ����������ŁA�ĉ��ł͂Ȃ��o�E�z�[���E�o�[�W�������Ƃ��B�J�[�g���ƃ��[�V�[�A�����ă_�[�l�C�̏o��̂�����A����ɋ߂����Ȃ菑�����܂�Ă��܂��B�J�[�g���͐��ނ����ŁA���܂ʼn��������Ƃ̂Ȃ��Â��L�����N�^�[�ɒ��킵�A�V�������͂������Ă��܂����B�_�[�l�C�͍ʐ��^���ŁA���͂̂���l�����Ɍ����B���V�[���̃R�X�`���[�����悭�������A���o�Ă��܂����ˁB���[�V�[�͐V�l�̍��T�ʉ����A�ꐶ�����ɉ����A�h���X�p����������Ɣ����������ł��B�Ȃɂ��������Ȃ��Ƃ����Ȃ����ł�����B �@��������������ł��邾���ɁA�J�[�g�����Ȃ��������܂ʼnA�T�ɐZ��̂��A���̗��R�͂Ȃ�Ȃ̂��A�^�₪�킭�̂ł��B�����m�肽���āA�����ǂ�ł݂��̂ł��ˁB����������A���R�͌���ɂ�������Ă��Ȃ��I�܂����̕ӂ��ߑ�̏����Ƃ͈Ⴄ�Ƃ���ŁA�܂�A���܂�Ȃ��烁�����R���[��������l�Ƃ����킯�B����l�Ƃ��ẮA�e�Ƃ̊W���A�ߋ��ɑ傫�ȍ��܂��������̂��Ƃ��A�ǂ����Ă����R��m�肽���Ȃ�̂ł����A���������������܂����l���Ƃ͖����Ȃ̂ł��ˁA�f�B�b�P���Y�́B�����������鑤�Ƃ��Ă͂���͑�ρB���������Ӗ��ł́A��n�����ނ��������ł��B
�@�����ĉf��ł����A����͖��m�ɃJ�[�g���̕���Ȃ����Ǝ��ȋ]���ɏœ_���i��A����͂͂�����J�[�g���B�����Ƀ��[�V�[������ލ\���ŁA�_�[�l�C�ɂ͂��܂�œ_�����Ă��Ă��܂���B�Ȃɂ��A�N���W�b�g�̃��C���L���X�g��3�l�ŁA�܂��J�[�g���A���Ƀ��[�V�[�A�����ă����[�Ȃ̂ł�����B�܂��A�J�[�g���͐l�C�o�D�̃_�[�N�E�{�K�[�h�i�w�x�j�X�Ɏ����x�ŗL���j�ł����A�����[�͖��D�Z�V���E�p�[�J�[�ł�����A��������R�ł��傤���B���[�V�[�̓h���V�[�E�e���[�g���ŁA���̐l�A���������̂ł��ˁB���m�N���Ȃ̂ł͂����荕���ǂ����͂킩��܂��A�Ƃɂ����_�[�N�B���[�V�[�ɂ̓u�����h�̃C���[�W���������̂ł�����Ƃт����肵�܂����B�����đ^�X�Ƃ��Ă���Ƃ������L�����Ƃ��Ă��āA�m�I�ōs���͂�����c�̋�������I�ȏ�����������Ă��܂����B�W�J�͂قڌ���ʂ�ŁA�铹���h�[�o�[�܂ŋ}���n�Ԃ̃V�[������n�܂�A���[�V�[��}�l�b�g���߂炦�悤�Ƃ���}�_���E�h�t�@���W���i�e���[�Y�j���~�X�E�v���X��������Ă��܂���ʂ�����܂��B�Ōオ�J�[�g���̏��Y�Ȃ̂́A�^�J���d�J�ł������B�����J�[�g�����Ō�ɋ��ɏ��Y����邨�j�q�ɋ����Ă��炢�A�L�X����V�[�������Ȃ苭������Ă��āA����邱�Ƃ̏��Ȃ������J�[�g���̐��U�̍Ō�̋~���Ƃ��āA�Ȃ��Ȃ������G���f�B���O�ł����B
�@���Ē��X�Ə����Ă��܂������A����́w�K�N�̕���x�����̐����p�A��������ƌ��܂�����B����Ɓu�v���_�N�V�����E�m�[�g�v�����|�[�g����\��ł��B �܂��A12���̃X�J�C�E�X�e�[�W�́w�x���T�C���̂�x�̃I���p���[�h�B�u���a�̃x����v���t�����C���Ō�����Ƃ����āA���̕ӂ��ǂ������Ă݂����ł��ˁB�ł́A����܂ł�������悤�I�@�l�j�ł����B |
| ���J�E���g�_�E�����W�o�b�N�i���o�[�i2001�N4��17���`2001�N7��1���j |
|
|||
| ���₢���킹�F �^�J���d�J�E�X�J�C�E�X�e�[�W�@tel.0570-000-290�i���j�x10:00�`17:00�j�@���₢���킹�t�H�[�� �ic�j��ˉ̌��c�ic�j��˃N���G�C�e�B�u�A�[�c�^���z�[���y�[�W�̊Ǘ��^�c�́A������Е�˃N���G�C�e�B�u�A�[�c���s���Ă��܂��B���z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă�����ɂ��ẮA���Ђ̋��Ȃ��A������E���ς��邱�Ƃ��ł��֎~���܂��B�܂��A��}�d�S����ѕ�ˉ̌��c�̏o�ŕ��ق��ʐ^�����앨�ɂ��Ă����f�]�ځA���ʓ����ւ��܂��B �����ԑg�̕ҏW�̊�b�ԑg�R�c�ψ����b�^�J���d�J�E�X�J�C�E�X�e�[�W�̒��쌠�ɂ��Ă̍l�����b�v���C�o�V�[�|���V�[�ɂ����b�L��������_��� |
|||
|
|
|||