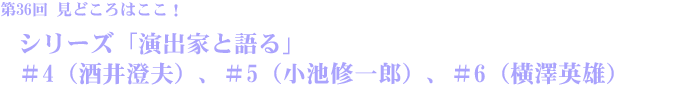 桜の季節が去り、もう初夏ですね。窓を開けると、初々しい新緑が陽に当たってキラキラ輝き、きれいです。季節は駆け足で巡っていきますが、みなさん、お元気ですか? さて今回久しぶりの番組チェックは、いつも楽しみな「演出家と語る」を取りあげましょう。演出家が縁の深いスターを迎えて、作品について、タカラヅカについて、そして出会いの思い出や近況を語り合うトーク番組です。今まで3本を取りあげてきましたが、今回はその後の3本をまとめてチェックしてみましょう。昨年末から今年春にかけて放送されたものですが、再放送の機会もあると思います。稽古場で、劇場で、密に接した者同士、示唆に富んだ言葉、知られざるエピソードなどが飛び出して興味が尽きません。ぜひ一度ご覧になってください。 まずは、酒井澄夫の回。ゲストは元・雪組の月影瞳と、星組・湖月わたる。月影は退団公演が酒井の『愛 燃える』、湖月はやはり酒井の『花舞う長安』に主演ということで、酒井お得意の中国物に関してのトークとなりました。収録は『花舞う長安』の大劇場公演と東京公演の間でしょうか、04年の11月22日とテロップが出ています。
60分の長いトークですからとても全部は紹介しきれませんが、まずは酒井の中国物に対する思い入れの深さが印象に残ります。そもそもタカラヅカに入ろうと思ったきっかけが、白井鐵三の名作『項羽と劉邦』だそうで、春日野八千代、南悠子を中心としたこの作品を観て、「タカラヅカってすごいな。こんなすごいものがこの世にあるのか。こういうものを一度やってみたい」と思い、それまで演劇に興味を持たなかったのがいきなり宝塚歌劇志望に変わったのです。酒井のレパートリーは、日本物から洋物までのショーから、洋物の芝居、ミュージカルまで幅広いのですが、近年公演の機会が少なかった中国物に対しては好き以上の使命感があるようです。『愛 燃える』はずっと温めていた企画だとか。 また酒井が入団したばかりのころ、菊田一夫から「お前もここの作者になるのなら、コスチューム・プレイをしなさい…タカラヅカは華麗な学芸会だからね、コスチューム・プレイをした方が間違いがないんだよ」と言われたとか。そこからタカラヅカの本分はやはりコスチューム物だと思い、その思いが中国物、そして日本物に向かったわけです。 またタカラヅカの中国物のセットは実は、いつも時代設定を超えて、いちばん華麗な花が咲いた唐の時代でやっていること、それもオリエンタルに憧れてパリでできあがったロココ・チャイナを、たぶん白井鐵三が逆輸入したものだ、という話はへえ! と目から鱗でしたね。湖月が演じた玄宗皇帝も、楊貴妃と出会ったころ史実では50過ぎなのを、舞台では30代くらいでやっているし、安蘭けいの安禄山など非常に太った人のはずが、若くスリムで美しい作りになっている…タカラヅカの舞台はやはりまず美しさが第一。でもそんな舞台を観て、私たちは感動する。タカラヅカの舞台は、虚から始まり、そこから人間の心の真実に迫るのだなと、話を聞きながら思いました。 曲づくりの苦心(『花舞う長安』で作曲を依頼した河村隆一とのいきさつも)、稽古の苦心、女役と男役(湖月が外部公演で女性を演じたときの発見…男性は何もしなくても男!)などが語られたあと、話は月影の現役時代に。 エトワールをするなど歌が得意と思われていた月影、実は歌は苦手で、音楽学校時代の成績は「下から数えた方が早かった」そうです。それが『ドニエプルの赤い罌粟』(バウ初主演で、真矢みきの相手役に抜擢された)のとき、演出の大関に「あんたは歌やで!」と言われ、そこから歌に携わる機会が増え、好きになったそう。そして同期娘役3人、風花舞、星奈優里で中心をつとめたロンドン公演の大変さ。1期上の湖月は男役でまだのんびりしていて、稽古場の彼女らを大丈夫かなと見守っていました。 そのロンドン公演後、同期娘役3人がぐるりと替わった組替え(純名りさが雪から花へ、月影が花から星へ、星奈が星から雪へ)が行われ、月影と湖月はしばらく星組で一緒の舞台を踏んでいます。この組替えは後に、純名の花組主演娘役、月影の星組主演娘役といった形で結実しますが(さらに後に宙組が創設され、雪組主演だった花總まりが宙組主演に移動し、月影が雪組主演にスライド、星奈が星組主演娘役に就任)、内示を受けたときは3人とも唖然呆然。声も出なかったようです。 湖月の話でおもしろかったのが、『国境のない地図』の新人公演主演でのピアノ演奏。ピアノの得意な麻路さきに合わせ、舞台上でのピアノ演奏のシーンがかなり長くあり、猛練習。「もう二度と弾きたくない」ほど練習して、「麻路さんの片手分を両手で、メロディーだけ弾いていたんです」と笑います。
酒井は日本物にも思い入れが深く、「レビューを作りたくて入団したが、とくに日本物をやろうと思っていた、家が料理屋をやっていて子どものときから歌舞伎などよく観ていたからね」…そこで湖月と月影から出たのが『恋の花歌舞伎』の名前。日向薫時代の星組のショーで、これは私も大好きでしたね。文字どおり「かぶいた」、新感覚のダイナミックなショーでした。 そして、100周年に向かって、伝統を大事にしなければいけない、その上で未来に向かおうという話でお終いとなりました。最後、湖月が「こうなったらやはり100周年を迎えていただいて、式典に呼んでいただいて」と話すと、酒井が「そのころ湖月さんにはまだまだ現役でがんばっていただいて」と返し、思わずずっこけた湖月でした。 次は『ヴァレンチノ』放送時に行われた、小池修一郎の回。87年の初演、92年の再演とヴァレンチノ役で主演した杜けあきと、再演のときのジューン・マシス役、紫ともが出演しています。と言っても、最初に紫だけが登場し(杜に所用があって遅れるという形)10分ほど小池と話し、杜がやってきて一言二言話し、紫が席を外すという構成。小池らしい凝った作りで、紫とは再演時の話、そして杜とは主に初演時の制作秘話が、今だから話せると言ったエピソードも含め、たっぷり語られます。
ともに実力派で、とくに演技に優れた杜と紫は、大人の役どころができる、いいコンビでした。杜は主演男役(当時はトップスターと言ってましたね)として、最初は鮎ゆうきと組んでいて、『華麗なるギャツビー』東京公演で鮎が退団したあと、『ギャツビー』の名古屋公演から紫と組みました。その紫がデイジーに入った『ギャツビー』名古屋公演を、実は私は観ているのですが、華やかなタイプの鮎とはまったく違ったデイジーで、これはこれで説得力と情感があり、杜の芝居もまたそれに呼応するかのように厚みを増し、芝居全体のテイストも変わっていたのに感心した覚えがあります。 小池が紫にある感慨をもって話したのですが、紫は初舞台の’84年『風と共に去りぬ』で、主席だったということもありいきなりの抜擢を受け、杜と組んで銀橋で歌ったのです。それだけ期待された紫ですが、そのまま主演街道まっしぐらとは行かず、組替えなど紆余曲折があったあと、入団8年目にして杜の相手役となったのです。初舞台で組んでから8年目、小池がいわく「最初から約束されたかのような」出来事でした。 紫は演技になんともいえない情感と奥行きがあり、私も気になっていた人だっただけに、もう主演は無理かとこちらの心が痛んでいた時期を経ての主演娘役就任は、とってもうれしかったですね。よかったな、どんな立場であろうとがんばっていれば誰かが必ず見ている、紫の就任は、大げさでなくそう思えたニュースでした。 小池は語ります…紫が、最終的に杜の相手役になったときは、初舞台時の共演を思い浮かべ、運命だと思った。『華麗なるギャツビー』も『ヴァレンチノ』も、一度出会いがあるが、ある紆余曲折を経て、最終的に結ばれる男女の話。その話を杜と紫のコンビがやる。現実と作品がオーバーラップして見えた。 それを受けて紫いわく…「カリンチョ(杜)と先生が、年下の男性を出してくださったりして、私の母性をうまく引き出してくれたんですね。まだまだ未熟だった私は、そういう所で助けられたと思います」。それを聞いたときの小池…なんともうれしそうな表情が印象的でした。 紫の小池の第一印象は、「やはり初々しかった」。そんな話をしているところに杜が登場。挨拶したあと、「中日劇場の『ギャツビー』でともこ(紫)と組んだときは、懐かしい人に会ったという感じがした。鮎と紫では個性が違うから、本当に芝居というのは何通りもあるなとすごくおもしろくて、私は何倍も楽しめた」。昨年のTCAスペシャル、東京で行われたOGバージョンの映像が流れ、そこで紫は『ヴァレンチノ』の”ラテンラバー”を歌っています。バウの歌だけどいちばん好きだったから歌ったという紫。そんな話のあと、今度は紫が退席。杜と小池のトークに変わりました。 それにしても久しぶりに顔を見た紫は、相変わらず歯切れがよい話しぶりで、元気そう。相変わらずチャーミングで、若いのにはびっくりでした。
さて杜と小池のトークには、初演の『ヴァレンチノ』の制作の裏話がたっぷり。小池が入団したのと、杜が音楽学校に入学したのが同じ’77年。いわば同期の二人ですから、お互い遠慮がありません。とくに杜の率直な発言には多弁で鳴る小池も押され気味で、その辺、見物でしたよ。それにしても杜は頭の回転が速い! おもしろいトークがいっぱいで、とても全部紹介できませんから、放送を観る機会があったらぜひご覧ください。 実は『ヴァレンチノ』は小池が入団10年目にして初演出した処女作。杜も入団7〜8年目で二番手になろうかという時期(稽古開始時が研7で、初日には研8になっていたと、小池が詳説している)。二人とも若く、演出家と生徒という立場を超えた同志的な結びつきのなか作り上げた作品でした。 「処女作で杜けあきという人と劇団が組ませてくれたことで、自分の道がある程度決まった」…小池はそう強調します。というのはミュージカルがやりたくて宝塚歌劇団に入ってた小池、入団時してすぐに「芝居とショー、どちらがやりたいか」と問われ、『ノバ・ボサ・ノバ』のようなプロローグもフィナーレもすべて物語の中に組みこまれている、そういう作品を作りたかったので「じゃぁショー」と答え、ショーの演出家につくことになって、そのままその道をたどってきたのです。ところが杜と組むことになり、『ヴァレンチノ』も最初はショーでもいいと言われ、しかしバウの2幕2時間という時間はショーには長すぎる、それに杜のいちばんの魅力はやはり演技だろう…そういうことでドラマ性の高いミュージカルをやることになったのです。「あそこでショーをやっていたら、たぶんショーの作家になっていた…だから杜さんが今の道を決めてくれた」というわけなのです。 実はそのとき一緒に『ギャツビー』の企画も出していたとか。しかしこれは著作権の問題があるのでダメでした。「ハリウッドとか1920年代の話がとってもやりたかったんです…『ヴァレンチノ』が決まったときは、あんな子がそんな物をやるんだ!? みたいな反応でしたね」。またヴァレンチノというキャラクターはかつて鳳蘭がショーの『セ・シャルマン』でやっていて、鳳のイメージが強く、杜でできるのか? という反応もあったとか。もちろん小池がやりたかったのは、「できあがったヴァレンチノでなく、夢を持ってアメリカに来て、思わぬ方向で成功するが、それに満足できないという、青年の成長物語」でしたが、それやこれやでプレッシャーが強い公演でした。
今では演出家は入団2〜3年目でデビューできていますが、そのころは10年かかる時代。小池のデビューは入団10年目でした。「20代を演出助手として捧げつくしているわけだから、無駄な時間とずっと思っていたけど、今はね、いろいろな経験をしてノウハウの引き出しをいっぱい身につけてからでよかったと思っている。5年くらいでやっていたらたぶん再演させていただくレベルにはもっていけなかったと思う」。 「やっぱり杜けあきだから成功した…本当にそう思っているんです。でもあなたって一を聞いて十を知る人じゃない? 何も言わなくてもサッとやってくれるのね。その後いろんなタイプのスターさんたちがいる、カンで動く人もいるし、積み重ねないとできない人もいるし、舞台では本当にすごいんだけど稽古場ではダメな人もいるしと分かってきたけど、稽古をしていてうまくできないと落ち込んでいたら、それは基準がカリンチョだからと言われましたよ(笑)」 それに答えて杜「…っていうか、心を感じるの。どの演出家でもそうなんだけど、言っている中を感じるというのかな、真意を想像できちゃうというか、それが楽しいんだよね。…先生も妥協しないし、私もそう。この(互いに攻めあうかけ合いの)重なりがあったから、あれができたと思うの」 振付に当時まだ無名だった宮本亜門をしたこと(再演ではフィナーレのみ。その宮本の振付場面、著作権の関係で販売ビデオではカットされていたのが、放送では入っている)、実は『エリザベート』のセットの原形となっている装置へのこだわり、杜が最初の場面で着ていたコートが由緒あるものだということ、イタリア人にイタリア語を習った話など、妥協を許さず、ハングリー精神でがんばった『ヴァレンチノ』制作の裏話が次々と飛び出します。 おもしろかったのが、物語で大きな役割を果たしていたオレンジの件。用意されていたスチロール製のものが大きすぎて、まるで夏みかんか八朔。樹になっている分はいいとして、手に取ったりするセットの方にはいくらなんでも大きすぎで、舞台稽古直前の休日、1日車を走らせて、あちこちのスーパーやホームセンターで、インテリア用のプラスティックのオレンジを買い集めたとか。 セリフ覚えがいいという話から、「私は感覚で生きている人間なので、そういう反応も敏感というかストレートというか、要するにちゃんと流れができてて、ちゃんと感情の表現ができている言葉はすごくよく覚えられるんですよ」と杜。それを聞いて小池はニコニコ顔です。 最後に大爆笑となった話を一つ、実況中継で…。 小池「初日が無事に開いてできたと思っていい気になったらそれで負けだよ! って言われた(笑)」。 杜「私が言ったの!! 最悪だな、私って(笑)」。 小池「そして絶対にダメだしに来なきゃいけないよって言われた(笑)。千秋楽までダメ出しをする先生もいるけど、開いたら旅行とかにいって逃げちゃう演出家もいるんだよね」 杜「…でも私ね、本当に見にきて欲しかったんだと思うの。このまんまいなくならないで、逃げるなよ! ってのがあったと思うのね。進化していく私たちを見てほしい。あと進化しすぎることもあるから、違う方向に…そういうのをちゃんと舵取りしてほしかったし。生意気言ってごめんなさいね。私が初舞台のころ先生がペーペーの演出助手で、怒られていたりしてるのをよく見ていたから、同志というか同級生で一緒に舞台を作っているというところがあったのね(笑)」 まさに同志のような丁々発止、遠慮のないトークでした。 最後は劇団を退職して数年、ベテラン演出家横澤英雄と、日本舞踊の名手、専科で理事の松本悠里のトークです。横澤が松本の初舞台、’57年の『春の踊り』を担当(第2部「花のエキスプレス」。頭にロケットをのせたロケットダンスの写真が見られる)。それからの縁というのですから、約半世紀のおつきあいです。二人で作った思い出の舞台から、互いのタカラヅカ入団のきっかけ、思い出に残る作品など、古き良き時代のタカラヅカの話題を中心に、おっとりと話が進みます。歴史的で興味深いエピソードと貴重な映像が満載ですが、そこからいくつかをご紹介しましょう。
まず横澤の入団のきっかけから。横澤は父親が創世記のプロ野球人、横澤三郎。宝塚でも野球をやっていてプロ野球とタカラヅカは縁が深かったそうで、父はタカラジェンヌと結婚。父親の兄弟も3人がタカラジェンヌと結ばれ、母と叔母3人が元ジェンヌという環境。当然幼いころから観ていて、白井鐵三も春日野八千代も幼いころからの知り合い。大学卒業時に阪急電鉄を受験したら、小林一三に「横澤の息子なら、タカラヅカへ行け」と言われ、歌劇団に入団したといいますから、筋金入りの家系です。白井鐵三に師事し、演出家として主に洋物のショーをやってきました。 横澤が入団してから6年目に松本が初舞台。実は横澤の妻も元タカラジェンヌで、松本と同期のバレエの名手。横澤は岡田茉莉子のファンで、似ていると評判だった彼女と結婚したと、これは松本の言。日本舞踊しかやってなかった松本はバレエを彼女から教わったとか。現在は宝塚随一の日舞の名手と言われる松本ですが、若いころはダンスもよく踊り、エイト・シャルマンという女役のダンスチームに選ばれ、危うくセリに落ちそうになった経験も。ほとんどずっと出演している海外公演の話、思い出の舞台と、松本の話は続きます。 松本の思い出の舞台の第一は『夜明けの序曲』のモルガンお雪。再演、初演ともに出演していて、ショーで日舞を踊るのがほとんどの松本にとって、セリフを言うお芝居は忘れられない経験だったようです。もう一つの思い出が、番組のセットに掛けられている、母自身の手により松が描かれた着物に関するもので、バウホールで2回行われたリサイタルで着ました。白地に墨のコントラストがなんとも美しく品格がありますが、映像の舞姿を観ると、実際に着て動くとまた魅力が増すのですね。すばらしいと感じました。 傑作なのが、横澤が春日野八千代と33日間ヨーロッパに行った話で、これは春日野がヨーロッパに行くことになり、誰かついていかないといけない、小さいころから知っていて「おもちゃをねだったこともある」、「英雄ちゃんならいいわ」と春日野の許可が出たという次第。外国旅行がまだまだ難しかった時代に、パリ、ロンドン、ウィーン、ローマと廻り、その経験は本当に勉強になったとか。これには、春日野が後に松本に「英雄さんと二人で行ったのにだーれも噂してくれへんかった」と語ったというオチがついていて、思わず笑ってしまいました。「春日野さんは本当のお嬢さんで、お金の勘定はふだんからなさらないから、国が変わるとお金が違うというの全然分からないの(笑)」…よき時代のスターというのはかくもこの世離れしているのかと、感心しました。 忘れられないスターたちとして横澤は、上月のぼる、大地真央を挙げていますが、その大地について松本。中南米公演のとき松本が歌詞を覚えていない大地を叱ったことがあったそうです。それを大地が月組の宴会で真似したとか。「月組の宴会でずっと私の真似をやるんですって(笑)…ミエコさん(松本の愛称)に注意されたとき、って(笑)。私は見ていないんですけど、いろんな方から聞きました」。現代っ子で聞こえた、いかにも大地らしい話です。
最後にとくに印象に残った言葉を紹介しましょう。 まず横澤。師匠の白井鐵三の言葉で横澤の座右の銘です。「タカラヅカでしかできない作品を書かなかったらダメだよ。本当の男がやったらよくなると言われたらダメだ。…男役がやらなくてはダメだ、という作品を作ることを心がけなさい」。 松本は「どんな踊りを踊らしていただいても、忘れてはいけないのは、タカラヅカではやはり品と格。それをなくしてはいけない…いつも肝に銘じて大事にしています」と述懐し、「いつまでたってもこれでいいということはないですね。勉強しても勉強しても、自分の未熟さが分かって…春日野先生もおっしゃるんですが、タカラヅカの難しさは枯れるということができないところ。枯れた芸は難しいですね。いかに若く見せるのも勉強の一つだなと思っています」。 まだまだ含蓄ある言葉が聞けますが、これはぜひ放送を見てほしいですね。 さて次は何を取りあげましょうか。初舞台生のことも取りあげたかったのですが、私がさぼっているうちにもう公演が終わってしまいました。彩輝直のサヨナラも目前です。そのあたりに注目して、次の番組チェックをお送りしましょう。次回をお楽しみに。ごきげんよう。M・Kでした。 |
| ■カウントダウン特集バックナンバー(2001年4月17日〜2001年7月1日) |
|
|||
| お問い合わせ: タカラヅカ・スカイ・ステージ tel.0570-000-290(日曜休10:00〜17:00) お問い合わせフォーム (c)宝塚歌劇団(c)宝塚クリエイティブアーツ/当ホームページの管理運営は、株式会社宝塚クリエイティブアーツが行っています。当ホームページに掲載している情報については、当社の許可なく、これを複製・改変することを固く禁止します。また、阪急電鉄および宝塚歌劇団の出版物ほか写真等著作物についても無断転載、複写等を禁じます。 放送番組の編集の基準|番組審議委員会|タカラヅカ・スカイ・ステージの著作権についての考え方|プライバシーポリシーについて|有料基幹放送契約約款 |
|||
|
|
|||





















